
こんにちは、ぽけるすです。
私は現役の小学校教師として働く傍ら、延べ、1000人以上の子供と接してきました。
その中で得たノウハウや知識を発信しています。
みなさんは子どもを褒めていますか?
特に同じ家庭で一緒に生活していると、相手の嫌なところばかりが目につくようになってしまうのが人間の性です。
「褒める」ことはコミュニケーションの基礎になる部分を担います。
基礎ができているからこそ、「叱る」「注意」が有効になります。
この記事を読んで、ぜひ「褒める」ことの重要性を理解して明日から実践してみてください。
褒める効果① 「信頼」が生まれる
人間は「好き」な人の言うことに従います。動物のようですがこれが事実です。
大人もそうです。嫌いな上司と好きな上司がいたら、同じことを言われても好きな上司に言われた方が納得しますよね。
ではこの「従いたくなる」「好意的な」関係をどう作るか。「褒める」ことで作っていきます。
「褒められる」→「関心を持って見てくれていることに気がつく」→「相手に好意を持つ」
このような、順で子どもは大人に好意を持ってくれるようになります。
よく褒めることはアクセル、叱ることはブレーキと言われますが、少し違っていると考えています。
「褒められる」ことで初めて「車に乗る」という基礎ができて、その上で「アクセル」「ブレーキ」は効果的に働くのです。
ますは、褒めて褒めて褒めて、「自分の言うことを聞いてもらえる好意的な関係」の構築が必須になるわけです。
褒める効果② 心が落ち着く
「セロトニン」は脳内で分泌される、精神を安定させるのに効果があると言われる神経物質です。恐怖・快楽などが行き過ぎるのを防ぎ、精神に安定をもたらしている物質だそうです。
セロトニンは他にも「日光浴」「適度な運動」などでも分泌され、減少すると「鬱」傾向になってしまうと言われています。
この、セロトニン、他にも分泌される(増やせる)方法があって、それは、「褒められる」ことです。
人間は褒められると脳内で「セロトニン」という神経物質が分泌されると言われています。
これは子どもも同じです。
褒められると、感情の浮き沈みがなくなる→いつも良い行動ができるようになる→また褒められていい行動ができるようになる。
といういいサイクルが回っていくようになります。
簡単に言うと、褒めれば褒めるほど、褒めることができる行動が増えて、さらに褒めることができる
と言うことです。
褒める効果③ 自尊感情がつく
「自尊感情」は「自信のある状態」と言い換えてもいいでしょう。
ただ、「自分は他の人より優れている」という感覚とは違っていて、「できる、できない関係なく自分が好きだ」という感情になります。
自尊感情が高い子どもは、「挑戦できる」「やり通せる」「他者を受け入れられる」ような特徴があります。そんな自尊感情が高い子どもがどのような大人になっていくか、言わずともわかりますよね。
自尊感情を高めるには「褒められる」ことが1番です。褒められる・認められることで「自信」が深まり、自分を好きになることができるようになるのです。
褒められすぎることのデメリットは?
褒められすぎることはデメリットもあります。
「褒め方」によっては、子どもが「褒められないとやらない」状態に陥る可能性もあります。
子どもの様子を見て、自律的に行動できるように促したいものです。
ですが、日本人の子どもは「あまりにも褒められ足りなさすぎる」というのが私の考えです。
褒め方についてはまた別の記事で。
【まとめ】子どもは褒められたりていない!
日本人の子どもたちは、諸外国の子どもと比べて、「自尊心」が低いと言われています。
私も教師として働いていて「褒められ足りていない」こどもの圧倒的な多さにいまだに驚きます。
日本人はいいのか悪いのか、「他人の評価」を気にします。保護者の方々も周りと比べて、恥ずかしい子ども子どもに育たないようにと、「しつけ」や「叱る」ことを通して「ブレーキ」を踏みすぎてしまっている人が多いように感じます。
ブレーキもアクセルも、効果的に効かせるには「信頼関係」が大切です。
子どもに信頼してもらえるように、まず「褒める」実践してみてください。
褒めすぎかな?褒め方がによってはダメになるんじゃないか?など、考える前にまず褒めてください。
褒め方を学ぶのはその後で結構です。
頑張ってみましょう!

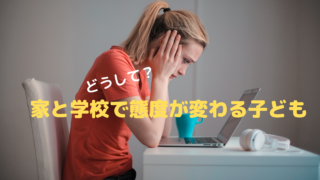


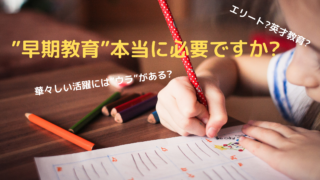


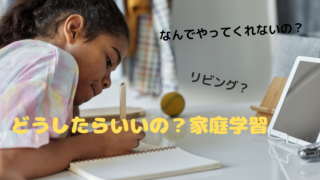
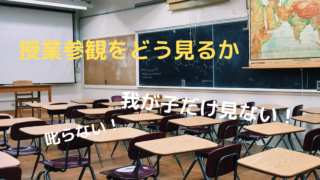







コメント